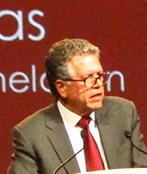
米国では、理由は不明だが、冠動脈疾患に対するキレート療法の施行数が増加しているという。しかしながら、その有用性は確認されていない。驚いたことに、有用性を示唆する機序さえ未確定だという。そのため、心筋梗塞後慢性期を対象とする無作為化試験TACT(Trial to Assess Chelation Therapy)が、NIH(国立衛生研究所)の出資により行われた。その結果、有意差はついたものの、キレート療法がプラセボに勝る有用性を確立するには至らなかったようだ。3日のLate Breaking Clinical Trialsセッションにて、マウントサイナイ・メディカルセンター(米国)のGervasio A. Lamasが報告した。
TACTの対象は、心筋梗塞発症後6ヶ月以上経過した、50歳以上の1,708例である。およそ4分の3は、β遮断薬など心筋梗塞後に対する標準的薬物治療を受けていた。これらはキレート療法群(839例)とプラセボ群(869例)に無作為化され、二重盲検法で追跡された。キレート療法にはEDTA(エチレンジアミン四酢酸)とアスコルビン酸を中心に10剤を用いるレジメンが用いられた。
その結果、一次評価項目である「死亡、心筋梗塞、脳卒中、冠血行再建術、狭心症による入院」はキレート療法群で相対的に18%の有意な減少が認められた(ハザード比:0.82、95%信頼区間:0.69~0.99)。加えて、上記イベントを個別に検討しても、一様にキレート療法群で減少傾向を示した。
試験中止につながる有害事象の発現は、両群で同等だった。
このような成績にもかかわらずLama氏は、この有用性を確認する別の研究が必要だと主張した。と言うのも、キレート療法群におけるイベントリスク・ハザード比の、95%信頼区間上限は0.99と「1」に近いうえ、本試験では17%が無作為化後に同意を撤回し試験から脱落している。これら17%が残っていた場合に有意差となる保証はない。
また、キレート療法群における一次評価項目減少数の半分弱を「冠血行再建術施行」が占めていた。二重盲検試験とは言え「主観的」な評価項目に結果が大きな影響を受けている点に、Lama氏は問題を感じたようだ。なお、「冠血行再建術施行」は「狭心症による入院」と並び、後から加えられた評価項目である。当初の一次評価項目は、「死亡、心筋梗塞、脳卒中、心不全入院」だった(心不全データは、今回報告されなかった)。
指定討論者であるアルバート大学(カナダ)のPaul W. Armstrong氏も、本試験は虚血性心疾患に対するキレート療法の有用性を確認したものではないと強調した。根拠として同氏は、まず、キレート療法により著明なイベント減少が認められたのは、全体の30%を占める糖尿病例のみだと指摘。非糖尿病例では、キレート療法群とプラセボ群の一次評価項目発生率に全く差はない。同氏はまた記者会見にて、キレート療法の有用性を評価するには、「腎毒性」に関するデータを見る必要があるとも述べた。
取材協力:宇津貴史(医学レポーター)
「他の演題はこちら」