
今冬のインフルエンザは、例年よりも早いペースで流行が伝えられています。インフルエンザ診療では、流行型への準備やワクチンの開始時期、新型コロナのような他の感染症との診断のポイント、リスクのある高齢者や小児への治療薬処方の考え方など、さまざまな臨床現場ならではの疑問などが発生します。今回は、インフルエンザ診療のお悩みについて、感染症診療のエキスパート、岡部信彦氏が、会員医師の皆さまからの質問に回答します。
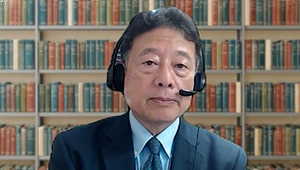
透析患者の平均年齢が上がって高齢化が進むなか、新たな透析診療の課題に直面している医師も多いのではないでしょうか。本コンテンツでは、CareNet会員医師から寄せられた腎不全・透析診療に関する疑問に対して、猪阪 善隆氏(大阪大学)がエビデンスと経験をもとに回答します。
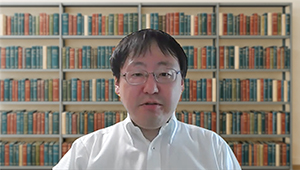
多岐にわたる原因で起こるめまいは、診療科を問わず遭遇する機会の多い症状です。とくに、中枢性や内科疾患を疑うべき「危険なめまい」を見逃さない鑑別は、あらゆる医師にとって重要な課題といえます。CareNet会員医師から寄せられた疑問をもとに、沖縄県立中部病院の井口 正寛氏が、めまい診療の基本から鑑別診断のポイント、さらには難治性めまいへのアプローチ、新たな疾患概念の「PPPD」までをわかりやすく解説します。

国内の潜在患者数は940万人以上とも言われる睡眠時無呼吸症候群(SAS)。治療の基本はCPAP(持続陽圧呼吸療法)となりますが、治療導入に至らない場合や治療を導入してもアドヒアランス不良となる場合があるなど、さまざまな課題が存在します。そこで、CareNet会員医師から寄せられたSAS診療に関する疑問について、富田 康弘氏(虎の門病院 循環器センター内科・睡眠呼吸器科)が解説します。
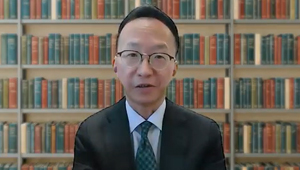
心不全バイオマーカーのなかで最も重要かつ日常診療における診断、予後予測、治療効果判定に用いられるBNP/NT-proBNP。近年増加している左室駆出率の保持された心不全(HFpEF) にもBNP/NT-proBNPが重要な意味を持つことから、2023年には「血中BNPやNT-proBNPを用いた心不全診療に関するステートメント」の改訂版が公表されました。また、「2025年改訂版心不全診療ガイドライン」でも、バイオマーカーの項で大きく取り上げられ、その活用度はさらに増していくことでしょう。そこで、BNP/NT-proBNP測定における実臨床で感じる疑問について、信州大学の桑原 宏一郎氏が解説します。
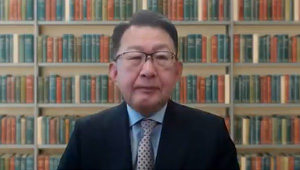
「肥満症」の治療は、従来、生活習慣改善による食事療法や運動療法、行動療法が行われてきました。しかし、現在では、治療薬や外科治療などで治すことができる疾患となっています。では、実診療でいつGLP-1受容体作動薬などの薬物療法の介入を行うべきか、どの段階で外科治療を考慮すべきか、精神疾患を合併している患者さんへの対応など悩ましいことがあります。こうした診療現場での疑問や困っていることについて、肥満症診療のエキスパートであり、日本肥満学会理事長である横手 幸太郎 氏(千葉大学 学長)が解説します。

アトピー性皮膚炎診療は昨年ガイドラインが改訂され、外用薬や生物学的製剤など、新たな薬剤が登場しています。それぞれの薬剤の使い分け、診療の注意点などについて、近畿大学の大塚篤司氏が解説します。