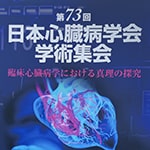
2019年9月より経皮的左心耳閉鎖デバイスWATCHMANが保険適用となり、それと同時に本邦の患者を対象としたJ-LAAOレジストリがスタートした。それから6年が経ち、これまでに7,690例が登録されてきた。その間にデバイスも進化を遂げ、今では3代目となるWATCHMAN FLX Proが主流となり、初期と比べより安全に左心耳閉鎖が実施できるようになってきている。第73回日本心臓病学会学術集会(9月19~21日開催)のシンポジウム「循環器内科が考える塞栓症予防-左心耳閉鎖、PFO閉鎖、抗凝固療法-」では、草野 研吾氏(国立循環器病研究センター 心臓血管内科部長)が「我が国の左心耳閉鎖術の現状-J-LAAOレジストリからの報告-」と題し、2025年3月までに登録された日本人におけるWATCHMAN最新モデルを含めた安全性・有効性を報告した。
J-LAAOレジストリは、全7学会(日本循環器学会、日本心エコー図学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会、日本脳卒中学会、日本不整脈心電学会)共同の非弁膜症性心房細動(NVAF)患者を対象とした経皮的左心耳閉鎖システムによる塞栓予防の有効性・安全性を調査した多施設レジストリ研究である。今回、脳梗塞スコア(CHADS2またはCHA2DS2-VASc)に基づく脳卒中および全身性塞栓症のリスクが高い患者、抗凝固療法が推奨される患者で、とくに出血リスクスコア(HAS-BLED)が3点以上の出血リスクが高い患者を選択基準とし、本レジストリ登録者のうち7,036例の急性期の手技情報、有害事象、術後の抗凝固療法などが解析された。留置後の薬物療法としては、海外試験のレジメンにならい、留置~45日はワルファリン+アスピリン、45日~6ヵ月は抗血小板薬2剤併用療法(DAPT)、その後はアスピリン単剤療法を推奨している。
主な結果は以下のとおり。
※いずれの結果も各デバイスでフォローアップ期間が異なる点には注意
・平均年齢は78.0歳(FLX Pro群:79.0歳)であった。
・各スコアの中央値は、CHADS2が3点、CHA2DS2-VAScが5点、HAS-BLEDが3点であった。
・アブレーション治療歴は約1/3にみられ、心房細動の種類としては発作性が2,780例(39.5%)、持続性が4,252例(60.4%)であった。
・モヤモヤエコー(smoke like echo)は1,971例(28.0%)にみられた。
・最終留置デバイスモデルは約11.3%で40mm、全体の2/3で31mmを超えるデバイスが選択されていた。
・手術情報について、手術成功例は97.9%、手術時間は平均52.0分(G2.5:60.0分、FLX:51.0分、FLX Pro:47.0分)で、透視時間も短縮傾向、造影剤投与量も減少傾向であった。
・心嚢液リスクはデバイスの形状変化に伴い減少し、G2.5は23例(3.1%)、FLXは40例(0.9%)、FLX Proは9例(0.6%)で認められた。
・術45日後の左心耳有効閉鎖率(complete sealもしくは残留血流の最大幅が5mm以下の症例)はG2.5で99.7%、FLXで98.3%、FLX Proで98.3%に認められた。
・術45日後の残留血液はG2.5で27%、FLXで13%、FLX Proで9.4%に認められた。
・有害事象について、術直後のデバイスごとの心タンポナーデと心嚢液貯留の発生率(G2.5、FLX、FLX Proの順)は、心タンポナーデで0.7%vs.0.2vs.0.1%、心嚢液貯留で1.7%vs.1.0%vs.1.1%であった。
・このほかの有害事象は、以下のような結果であった。
◯デバイス血栓3.2%(G2.5:36例[4.8%]、FLX:170例[3.7%]、FLX Pro:19例[1.3%])
◯うっ血性心不全4.5%(73例[9.7%]、226例[4.9%]、21例[1.4%])
◯脳卒中2.5%(36例[4.8%]、131例[2.8%]、11例[0.7%])
・死亡者数は全体で415例(5.8%)、G2.5では92例(12.2%)、FLXでは298例(6.5%)、FLX Proでは25例(1.7%)であった。
・デバイス移動は全11例(0.16%)、機器の外科的摘出は全9例(0.13%)、経皮的デバイス抜去は全3例(0.04%)であった。
本結果について草野氏は「患者背景をみると、日本人は米国人と比べて発作性心房細動症例の割合が少なく、左心耳入口部が比較的大きい。その点が選択デバイスの大きさに反映されていた。残留血液量も減少傾向にあり、心タンポナーデの発生率の少なさからも安全に手技が行われていたことがうかがえる」とコメントした。外科的摘出の原因として、デバイス血栓・脱落、左房血栓などがみられた点については、「1年以上経過後に発生していることに留意が必要」とし、加えて「FLXでは手術当日にデバイス血栓を生じている症例が複数例あった。一方で、留置後2年後にも生じているケースも散見される。デバイス血栓を発症した患者はシリアスな病態には至っていないものの、これらの結果を踏まえて継続的なフォローアップを行ってほしい」と強調した。なお、いずれの結果を見るうえで、FLX Proは発売からフォローアップまでの期間が短いことには注意が必要である。
国内ガイドラインでの推奨は…
日本での左心耳閉鎖術に関する推奨は、『2021年JCS/JHRSガイドラインフォーカスアップデート版不整脈非薬物治療』
1)において、「NVAFに対する血栓塞栓症の予防が必要とされ、かつ長期的な抗凝固療法の代替が検討される症例に左心耳閉鎖術を考慮してもよい(推奨クラスIIB、エビデンスレベルB)」となっていた。しかし、2024年にフォーカスアップデート版として公開された『2024年JCS/JHRSガイドラインフォーカスアップデート版不整脈治療』では、症例数の乏しさから左心耳閉鎖術に関する項目に変更は示されず“長期的な抗凝固療法が必要ではあるが、出血リスクが高く抗凝固療法が適切ではない患者においては、左心耳閉鎖デバイスを用いた経皮的左心耳閉鎖術や胸腔鏡下左心耳閉鎖術を症例に応じて考慮してもよい”(p.59)にとどまっている。これについて草野氏は「J-LAAOを経年的に見ても、植込み対象での出血2次予防の割合が減少し、塞栓予防目的の植込みが増加している。今後は海外ガイドラインに準じて、脳梗塞高リスク例への広がりが期待される」と述べた。
最後に国内の状況について、同氏は「米国と日本では左心耳閉鎖術の実施件数に10倍もの差があり、欧米に比べると国内での実施件数は少ない。またレジストリでは、少数ながら脱落が外科手術に至った例があり、安全を心がけた植込み術も重要である」と締めくくった。
(ケアネット 土井 舞子)