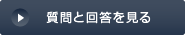1969年9月14日生まれ。博士(医学)、博士(工学)。1994年3月慶應義塾大学医学部医学科卒業後、同大学病院にて研修94年4月同大学大学院医学研究科博士課程。96年11月ハーバード大学医学部放射線科心臓血管造影およびIVR部門留学(~99年)。98年4月同大学医学部助手。04年4月同大学理工学部機械工学科・鈴木哲也研究室共同研究員および医療班チームリーダー。05年4月国家公務員共済組合連合会立川病院放射線科医長。08年4月東邦大学医療センター佐倉病院放射線科講師。09年8月同病院放射線科准教授。日本血管内治療学会評議員。日本IVR学会代議員、他。10年日本学術振興会 榊奨励賞受賞、第96回北米放射線学会Certificate of Merit受賞、他多数。
低侵襲治療としてIVRカテーテル治療に大きな魅力を感じた

放射線科領域を大別すると、X線検査、CT、MRI、核医学検査などに代表される放射線診断学とがん治療に代表される放射線治療学があります。CT、MRIなどが登場する前から存在した「血管造影法」は、私が専門とする放射線診断学の根幹です。血管のない臓器は存在しないため、古くから重要な診断法として発展してきました。
しかしながら、CT、MRIなどの医療機器の技術革新によって血管造影の役割も変わってきました。皮膚に局所麻酔をしてほんの2㎜だけの傷をつけるだけで血管内に「カテーテル」と呼ばれる管を挿入し、臓器に直接アプローチできるので、たとえば循環器領域であれば心臓にアプローチして狭心症や心筋梗塞を治す。消化器領域では、肝臓がんであれば肝動脈塞栓術のように大腿動脈から患部のすぐそばまで細いカテーテルを挿入して抗がん剤を流して腫瘍を兵糧攻めにする。脳神経領域では、急性期の脳梗塞の血栓溶解療法や動脈瘤を詰めることもできます。
また、下肢の動脈硬化の場合、風船付きカテーテルを挿入し直接狭くなった血管を広げ、歩けなかった患者さんが歩いて帰えれるようになる。CTやエコー、MRIなどの画像支援の下に血管内だけでなく臓器を直接穿刺して治療する。画像を使った血管内治療および血管以外の臓器などに対する、画像支援下の低侵襲治療、これが私の専門領域です。
医学の世界に入った当初から、IVR(インターベンショナルラジオロジー)に興味があり魅力を感じていました。これからの治療は、身体に大きくメスを入れて手術するだけではなく、患者さんに優しい治療でありながら効果的な治療が求められています。
カテーテルの技術にせよ、医療器具にせよ、どんどん進歩してくるであろうと考えました。その進歩と共に、カテーテル治療が今後の医療現場において主流になってくるのではないかとも考えていました。それは現実になってきていると確信しています。
IVR治療で劇的に変わる患者さんのQOL

IVRでできることは血管を開く、詰める、溶かす、生検のための組織を切除して取り出す、直接腫瘍を穿刺して治療する、簡単にいうとこれらが主な分野です。具体的には、動脈硬化で詰まった血管を開き、血栓で詰まった血管を溶かすことができる。体を大きく切開することなく組織を取り出し診断を確定する、ドレナージといって体内の深い部分の膿をCT・エコー・MRIで見ながら吸い取る。詰めるは塞栓術といって、肝臓がん治療の他、体の中で緊急出血した場合、血圧が低下し、身体を大きく開くことはできないので、救急治療として金属のコイルを詰めて止血し、一命を救うこともできます。
今までは大きく開腹、開胸しなくてはならなかった手術が、IVR治療によって足の付け根や腕の部分を局所麻酔で2から3mm切開し、動脈や静脈にカテーテルを挿入して治すことができるようになっています。これにより患者さんの入院日数は劇的に短縮されました。局所麻酔のため危険性も減りますし、入院期間も短くなり、痛みが少ないなど多くのメリットがあります。
心臓疾患の場合、以前ならば最低でも1から3ヵ月の入院を余儀なくされましたが、IVR治療では、長くて10日、われわれは3日から1週間入院を目安にしています。ただし、入院期間が短縮されたからといって、簡単な病気だったと勘違いはしないでほしい。血管内で手術は行われていますから、それなりのリスクがあることも十分知っておいてほしいと思います。
患者さんにとって簡単そうに思えるIVR治療ですが、医師としては熟練した手技と全身疾患に対して知識や経験がないとできない分野です。実際に治療を行えるようになるまでには、綿密なトレーニングが必要です。東邦大学では後期研修医あるいは大学院生の1年目から血管内治療のトレーニングを本格的に重ねてもらいます。われわれの科では、画像診断もやりながら低侵襲の治療をする、研究にも取り組み積極的に国内外の学会で発表するという3本の柱を忘れることなく、必死で若手の医師が毎日を過ごしています。
臨床医としての経験を活かした研究開発

私がこの世界に入った時にはすでに、血管内治療のデバイスであるステントやバルーンの8割が輸入品でした。許認可の問題もあって、欧米の製品を平均2年遅れで買わなければいけない現状があります。その上、必ずしも日本人に適しているデバイスではありません。日本人にとって使いにくくて直してもらうにしても、製品ができあがってくるまでに1年、2年、3年かかる場合もあります。目の前の患者さんを治せるツールがあるのに、サイズが合わないだけで使えないという現実にジレンマを感じていました。
私が慶應の研修医だった当時、恩師で、放射線医の第一人者であり、日本のIVRの父ともいえる平松京一教授(当時)の計らいで、医師になってから2年半後にハーバード大学で研鑚(けんさん)を積むようにと言われました。そこで約3年半、留学することになってしまいました。研修医が終わったばかりで、何の実力もないし、研究歴もなかった。渡米前には、多くの上司にも心配されました。ハーバード大学で最初の数ヵ月はお客さん扱いでしたし、もう帰国しようかとどまろうかと考えながら細々と実験を始めました。その実験データを基に数ヵ月後に書きあげたプロトコールが運良く認められて潤沢な公的研究費が与えられて、それをきっかけに状況が変わりました。
そこのチームのチーフに任命され、血管の中の遺伝子治療研究が始まりました。詰まった心臓血管の中にステント(金属のメッシュ状の筒)を入れると、再狭窄が起こります。ステントは血流を劇的に改善しますが、血管を無理に開くため血管の内皮細胞や血管平滑筋細胞に傷がつきます。血管には破れると修復する作用があって、傷を修復する過程で、金属の周囲に血栓が付き、その刺激が過剰平滑筋細胞の増殖を促し、血管がまた詰まってしまうのです。それを治すために特殊なバルーンカテーテルというのを用いてそこから薬剤を出す。当時は、ステント留置後、20%から40%は半年後には詰まるといわれていました。
確かに、血管内の遺伝子治療は実験的に成功し、米国IVR学会やNIHなどで受賞しました。けれども、やはり金属ステントそのものの留置が「諸刃の剣」だということに気づき、帰国後、材料工学の研究を独学で始めました。体になじみにくい金属が、長期的によい成績をだせるわけがないと考えたからです。しかしながら、金属の特性としてしなやかさや耐腐食性などを上回る素材はなかなかありません。それならば、既存のものにコーティングを施したらどうか、と考えました。ただし、コーティングするにしても体に害を及ぼすものでは当然使えません。行き着いたのがダイヤモンド系のコーティングでした。ダイヤモンドは、「物質の王様」といわれるだけあって、非常につるつるしているばかりではなく、耐摩耗性という特性があり、さらに炭素は身体を構成する成分の一つなので、人体に悪影響を及ぼしません。
現在、主流となっている薬剤溶出性ステントから出てくる薬剤は薬効が強く正常の血管内皮細胞にダメージを与えるものが主流ですが、ダイヤモンドというのは化学的に安定しているばかりでなく、細胞に毒性を与えない特性を持っています。われわれは、さらにダイヤモンド系コーティングにフッ素を混在させることによって、血液の付着も防げることを初めて発見しました。つまり、フッ素を添加したDLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)というコーティングは、血液をはじき付着を防ぐので、血栓ができにくい。さらに、血管内に残るのは炭素を主流とするダイヤモンド系素材なので、身体に悪いものではありません。
これらの研究開発には、医学の知識だけではなく工学知識の力が不可欠でした。そこで、臨床医の立場で工学との通訳をしなければいけないと痛感しました。なぜならば、工学の思考と医学の研究者の思考回路はまったく違うからです。ですが、工学者も研究の応用の幅を広げたいと考えているし、医学者もテクノロジーを利用する考えが必要です。互いの歩み寄りを円滑にするために、私は医学部の栗林幸夫教授のご指導の下、医学博士を取得し、その後、工学部の鈴木哲也教授の下で工学博士を取得しました。
これからも研究開発において、医工連携のための通訳になれたらと思いますし、私に続く若い医師や研究者を育成することに力を注いでいます。
ゼロからのスタートに惹かれ挑戦

慶應からこちらへ来たのは、ここはほぼゼロからということに興味を持ちました。現在の教室の寺田一志教授の誘いもあり、今までやってきたことをここで一度リセットして挑戦してみるのもいいだろうと考えました。
慶應もいい環境ではありましたが、東邦大学の伝統と自由な気風、研究に対しても「自由にやれ」というムードがありました。特に、東邦佐倉病院では、他の臨床医の方々も、慶應から来た新参者にすごく親切にしてくれて、雰囲気もよかったし、全体的にやる気の気運が高まっている瞬間でした。
今では県内でもトップクラスのIVR症例数を誇る施設になりつつありますが、こちらに来た当時はIVR治療もあまり積極的に行われていませんでした。それでも、循環器センターや消化器センターなど各診療科の多くの先生のご協力があって、現在にいたっています。これは、東邦大学の気風とセンター単位で行われるチーム医療にうまく融合した結果だと思います。前病院長の白井教授が臨床・研究に対する基礎を構築し、現在の田上病院長を中心にした執行部の積極的な支援の賜物だと思います。
当院循環器センターの専門外来である「血管内治療・IVR外来」は、循環器内科医、心臓血管外科医、臨床検査医、放射線科医、心臓リハビリ医、形成外科医、糖尿病代謝内科医など本当の意味でのチーム医療ができるように構築してきました。カンファレンスの意思が医師同士の間で一貫しているというのは、患者さんにとっても安心できることだと思います。
臨床としては主に肝臓がんや救急出血や動脈瘤などの塞栓術と下肢の閉塞性動脈硬化症(ASO: arteriosclerosis obliterans)に伴い、詰まってしまった血管の血管形成術がメインです。糖尿病や動脈硬化で足が壊死してしまうのを治療するのがメインです。私にとって医療器具の研究はライフワークですが、実は臨床が9割。この臨床の経験があるからこそ研究のテーマが明確に打ち出せるのだと思います。
これからは教育にも力を注ぐ

私がこれから望むものは、若い人の教育です。まだ私も若いですけど……(笑)。若い人を教育するということは、自分が教育されることでもあります。教えるというのは、教えられることでもあります。先入観のない眼で若い人と日本から何かを発信したい。
座右の銘は「感謝して今日もニコニコ働きましょう」。決して一人で仕事をしているのではなく、周りのスタッフ、上司、親、自分の周りの人すべてが笑顔でいられる医療をやりたい。そのために臨床はもちろん、研究や医療器具の開発もしたい。
若い医師には、どんどん広い世界を見て、自分のアイデンティティ、日本人であるとか医師になるという明確な自覚を持ってほしい。勇気を持って新しいことにもチャレンジしてほしい。それらを一緒にやっていきたい。だからうちの科では工学部との交流や留学なども積極的にプログラミングしています。若いうちから何でも経験させ、国際学会発表も全員が入局2年以内に経験するように指導しています。
敵は病気なので、最高の技術、最高の人間性、患者さんを治したいという気持ちを強く身につけてほしいと考えています。是非、そんなピュアな高い志を持った若い先生と学閥や分野を越えて一緒に働きたいという希望を持っています。
質問と回答を公開中!